「あれ?全席指定のはずなのに、デッキに立ってる人がいる…」
のぞみや、はやぶさに乗った時、こんな光景を目にしたことはありませんか?全席指定なら、全員が座席に座っているはず。なのに、なぜか車両の連結部分(デッキ)に立っている人がいる。「座席がないのに乗れるの?」「料金はどうなってるの?」と疑問に思いますよね。
実は、全席指定の新幹線でも「立ち乗り」は可能なんです。ただし、これにはちゃんとしたルールがあります。指定席を予約していなくても乗車券と特急券があれば乗れる、でも立つ場所には制限がある、料金は指定席料金を払わなくていい…など、知っておくべきポイントがたくさん。
この記事では、「新幹線 全席指定 立ってる人」の謎を徹底解明。デッキ乗りとは何か、立ち乗りになるパターン、料金はどうなるのか、どこに立っていればいいのか、乗り遅れた時の対処法、返金・補償のルールまで、すべて詳しく解説します。
急な予定変更で指定席を取れなかった時、乗り遅れてしまった時。この記事を読んでおけば、慌てずに対処できます。全席指定の新幹線で立ち乗りする時の完全ガイド、始めます。
✈️ 旅費を少しでも安くしたい方へ
(PR)予約前に「使える割引」がないかだけ、先に確認しておくと安心です。 クーポン有無で総額が変わることも
※提携先サイトへ移動します(内容は時期・条件により変わる場合があります)
新幹線の全席指定なのに立ってる人がいる!その理由とは?

全席指定の新幹線でも「立ち乗り」は可能
まず結論から言います。全席指定の新幹線でも、「立ち乗り」は可能です。
「え、全席指定なのに?」って驚きますよね。私も最初は驚きました。全席指定って、全員が座席を持っているイメージですから。でも実際には、指定席を予約していなくても、乗車券と特急券さえあれば新幹線に乗ることができるんです。
初めて全席指定の新幹線で立ち乗りしている人を見た時のことを、今でも覚えています。私は東京から新大阪へ向かう「のぞみ」の指定席に座っていました。トイレに行こうとデッキに出たら、そこに3〜4人が壁にもたれかかって立っていたんです。「え?この人たち、なんで立ってるの?全席指定なのに」と不思議に思いました。
後で調べてわかったのですが、全席指定というのは「全ての座席が指定席」という意味であって、「指定席を持っていない人は乗れない」という意味ではないんです。指定席を持っていなくても、特急券があれば乗車はできる。ただし、座席はないから、デッキに立つことになる。これが「全席指定なのに立ってる人がいる」理由だったんです。
ただし、座席には座れません。デッキ(車両の連結部分)に立って移動することになります。これが、いわゆる「デッキ乗り」や「立ち乗り」と呼ばれる乗車方法です。
JRの規則では、指定席を予約していない乗客でも、特急券を持っていれば新幹線に乗車することが認められています。ただし、座席を利用する権利はないので、立って移動するしかないというわけです。
【重要ポイント】
・全席指定の新幹線でも立ち乗りは可能
・乗車券+特急券があれば乗れる
・ただし座席には座れない(デッキに立つ)
・指定席料金は不要だが特急料金は必要
なぜ座席があるのに立っている人がいるのか
「座席があるのに、なぜわざわざ立っているの?」と思いますよね。立っている人たちにも、それぞれ事情があります。
最も多いのが、「指定席を取れなかった」ケース。繁忙期や週末、人気の時間帯は、指定席が早々に売り切れてしまいます。でもどうしてもその時間に移動しなければならない。そんな時、立ち乗りを覚悟で新幹線に乗る人がいるんです。
私の友人が、まさにこのパターンでした。彼は東京で仕事をしていて、急きょ大阪の実家に帰らなければならない事態が発生したそうです。親が倒れたという連絡を受けて、慌てて新幹線を予約しようとしたのですが、その日の「のぞみ」はすでに満席。「ひかり」も「こだま」も満席。どうしようかと悩んだ末、立ち乗り覚悟で特急券だけを買って、新幹線に飛び乗ったそうです。東京から新大阪まで約2時間半、ずっとデッキに立ちっぱなし。「足はパンパンになったけど、親に会えたから良かった」と言っていました。
次に多いのが、「乗り遅れた」ケース。予約していた指定席の列車に乗り遅れて、次の列車に飛び乗った。でも次の列車は満席で座席が取れない。結果的にデッキに立つことになります。
乗り遅れる理由は本当に様々です。会議が長引いた、電車が遅延した、家を出るのが遅れた、駅で迷った…。どんな理由であれ、予約していた列車の発車時刻に間に合わなければ、その指定席は無効になります。でも、JRには救済措置があって、当日中の後続列車に立ち乗りで乗ることができるんです。これは本当にありがたいルール。「乗り遅れたら全額無駄になる」ではなく、「立ち乗りでも目的地には行ける」というのは、かなりの安心材料です。
また、短距離移動の場合は、わざと指定席を取らずに立ち乗りする人もいます。例えば、東京から品川、新横浜から名古屋など、1〜2駅だけ乗る場合。「10分程度なら立っていても平気」という判断で、指定席料金を節約するわけです。
立っている人たちの事情は様々。でも共通しているのは、「どうしてもその列車に乗る必要があった」ということです。
のぞみ・はやぶさ・かがやきは全席指定
全席指定の新幹線には、どんな列車があるのか。代表的なものを挙げると、次の通りです。
| 路線 | 列車名 | 区間 | 座席構成 |
|---|---|---|---|
| 東海道・山陽新幹線 | のぞみ | 東京〜博多 | 全席指定(一部に自由席あり) |
| 東北新幹線 | はやぶさ | 東京〜新函館北斗 | 全席指定 |
| 北陸新幹線 | かがやき | 東京〜金沢 | 全席指定 |
| 九州新幹線 | みずほ | 新大阪〜鹿児島中央 | 全席指定 |
特に「のぞみ」は、東海道新幹線の主力列車。東京〜新大阪間を最速で結ぶため、ビジネス客や観光客に大人気です。ただし、のぞみにも一部の列車には自由席車両があります(1〜3号車)。でも、繁忙期は自由席も満席で立つことになることが多いです。
「はやぶさ」や「かがやき」は完全な全席指定。自由席車両がありません。だから、指定席を取れなかった場合は、必然的にデッキに立つことになります。
自由席がある列車との違い
全席指定の列車と、自由席がある列車の違いを理解しておきましょう。
自由席がある列車(ひかり、こだまなど)
- 自由席車両がある(通常1〜5号車)
- 指定席を取らなくても自由席に座れる可能性がある
- 自由席特急料金は指定席より安い
- 混雑時は自由席も立ち乗りになる
全席指定の列車(のぞみ、はやぶさ、かがやきなど)
- 全車両が指定席(自由席なし)
- 指定席を取らないと座席がない
- 立ち乗りの場合でも特急料金は同じ
- 繁忙期は指定席が早々に売り切れる
自由席がある列車なら、まだ座れる可能性があります。でも全席指定の列車は、指定席を取らない限り、確実にデッキに立つことになります。この違いは大きいです。
繁忙期は立ち乗りが増える理由
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆の時期。こうした繁忙期には、デッキに立っている人が急増します。
理由は明白。指定席が売り切れるからです。
繁忙期の新幹線は、1ヶ月前の発売開始と同時に人気の時間帯の指定席が売り切れます。特に、帰省ラッシュのピーク時間帯(12月29日の夕方、1月3日の夕方など)は、発売開始から数時間で完売することも珍しくありません。
「どうしても帰省したい」「この日に移動しなければならない」という人たちは、指定席が取れなくても新幹線に乗ります。結果、デッキは立ち乗り客でいっぱいになります。
私も一度、年末の東京発の「のぞみ」に立ち乗りしたことがあります。デッキには10人以上の立ち乗り客がいて、身動きが取れないほどでした。名古屋まで約1時間40分、ずっと立ちっぱなし。あの時は本当に疲れました。
さらに、繁忙期の立ち乗りが増える背景には、「自由席も満席」という事情があります。のぞみには一部の列車に自由席車両(1〜3号車)がありますが、繁忙期はこの自由席も満席。発車30分前には自由席の列に長蛇の列ができ、座れない人が続出します。「自由席がダメなら指定席を…」と思っても、指定席も売り切れ。結果的に、立ち乗りを選ぶしかない、という状況になるんです。
実際、2024年の年末年始(12月28日〜1月5日)には、JR東海の東海道新幹線の指定席予約率が95%を超えたと報道されました。ほぼ満席状態。こうなると、立ち乗り客が増えるのも当然です。
繁忙期に新幹線を利用するなら、できるだけ早めに指定席を予約するのが鉄則。発売開始日(乗車日の1ヶ月前)の午前10時に、スマホやパソコンで予約できるよう準備しておきましょう。数分の遅れが、指定席を取れるか取れないかの分かれ目になります。立ち乗りは最後の手段と考えておきましょう。
「デッキ乗り」って何?全席指定でも立って乗れるのか

デッキ乗りとは車両の連結部分に立つこと
「デッキ乗り」という言葉を聞いたことがありますか?新幹線の利用者の間では、よく使われる表現です。
デッキとは、新幹線の車両と車両をつなぐ連結部分のこと。ドアを開けて次の車両に移動する時に通る、あのスペースです。通常、デッキには次のような設備があります。
- トイレ
- 洗面台
- 荷物置き場
- 自動販売機(車両による)
- ゴミ箱
デッキは本来、トイレに行ったり、車両を移動したりするための通路です。でも、指定席を持っていない乗客は、このデッキに立って移動することになります。これが「デッキ乗り」です。
デッキの広さは、だいたい3〜4平方メートル程度。立って移動するには十分なスペースですが、長時間立ち続けるには少し狭く感じるかもしれません。
デッキの構造は、新幹線の車両によって少しずつ異なります。最新のN700系では、デッキがやや広めに設計されていて、荷物置き場も充実しています。一方、古い車両では、デッキが狭く、荷物を置くスペースも限られています。運が良ければ広いデッキに当たりますが、運が悪いと狭いデッキで窮屈な思いをすることになります。どの車両に当たるかは運次第です。
デッキには窓がある車両と、ない車両があります。窓があるデッキなら、外の景色が見えるので、立ち乗りでも少しは楽しめます。富士山が見えたり、田園風景が広がったり。窓がないデッキだと、ただ壁を見つめて時間が過ぎるのを待つだけ。長時間の立ち乗りでは、窓の有無が意外と大きな違いになります。
デッキ乗りは正式には認められていない
実は、「デッキ乗り」は正式にはJRが推奨している乗車方法ではありません。
JRの規則では、指定席を持たない乗客が新幹線に乗ることは認められています。でも、デッキに長時間立ち続けることは、本来想定されていないんです。
なぜなら、デッキは通路であって、乗客が長時間滞在する場所ではないから。トイレに行く人、車両を移動する人、車掌さんが巡回する時など、デッキは常に人が通ります。そこに立ち乗り客がいると、通行の妨げになる可能性があります。
JRの公式見解としては、「指定席を予約してご乗車ください」というスタンス。でも、実際には指定席が取れない状況もある。だから、黙認されているというのが現状です。
この「黙認」という状況が、少し曖昧で不安になる人もいるかもしれません。「本当に乗っていいの?怒られないの?」と心配になりますよね。でも安心してください。特急券を持っている限り、デッキに立って乗車すること自体は規則違反ではありません。客室の通路に立ったり、座席に勝手に座ったりしない限り、車掌さんに注意されることはまずありません。
ただし、混雑時には車掌さんから「デッキが混雑しているので、他のデッキに移動できますか?」と声をかけられることがあります。これは注意というよりは、乗客の安全と快適性を確保するための配慮です。素直に従えば問題ありません。車掌さんも、立ち乗り客が困っていることは理解しているので、威圧的な態度を取ることはありません。むしろ、「大変ですが、よろしくお願いします」と労いの言葉をかけてくれることもあります。
実際にはどれくらいの人がデッキ乗りしているのか
では、実際にどれくらいの人がデッキ乗りをしているのか。
平日の昼間、閑散期なら、デッキ乗りしている人はほとんどいません。1車両に1〜2人いるかいないか、という程度です。デッキはガラガラで、むしろ「なぜわざわざデッキに?」と不思議に思うレベル。短距離移動の人や、電話をかけたい人が、たまにデッキにいる程度です。
でも、週末や連休、繁忙期になると状況は一変します。1つのデッキに5〜10人が立っていることも珍しくありません。特に繁忙期のピーク時は、デッキが立ち乗り客で埋まります。
私が実際に目にした光景では、年末の東京発「のぞみ」のデッキに、15人以上が立っていました。身動きが取れないほどの混雑。トイレに行きたい人が通るのも一苦労、という状態でした。デッキの床に座り込んでいる人もいて、「これはもう立ち乗りの域を超えている」と感じました。
さらに興味深いのは、立ち乗り客の属性です。繁忙期のデッキを観察すると、ビジネススーツを着たサラリーマン、大きなスーツケースを持った旅行客、帰省らしき家族連れ、学生グループなど、本当に様々な人がいます。共通しているのは、「どうしてもこの列車に乗る必要があった」という事情。みんな、立つのは覚悟の上で乗車しているんです。
ちなみに、立ち乗り客の中には、「座席に座っている人を羨ましそうに見る人」もいます。客室のドアの小窓から、座席でリラックスしている人たちを眺めて、「ああ、指定席を取っておけばよかった…」と後悔している様子が見て取れます。私も立ち乗りした時、同じことを思いました。次は絶対に指定席を取ろう、と。
時期や時間帯によって、デッキ乗りの人数は大きく変わります。でも、繁忙期にはかなりの人数が立ち乗りしている、というのが現実です。そして、その多くの人が「もう二度と立ち乗りはしたくない」と思っているはずです。
車掌さんに注意されることはあるのか
「デッキに立っていて、車掌さんに注意されないの?」と心配になりますよね。
基本的には、注意されることは少ないです。車掌さんも、指定席が取れない状況があることを理解しています。デッキに立っている乗客に対しては、黙認しているのが一般的です。
ただし、次のような場合は注意されることがあります。
- 通路を完全にふさいでいる
- トイレのドアの前に立っている
- 客室の通路に立っている
- 荷物を広げて他の人の邪魔になっている
こうした迷惑行為をしていると、車掌さんから「少しずらしてください」「客室の通路には立たないでください」と注意されます。
私の友人は、客室の通路に立っていたところ、車掌さんに「デッキに移動してください」と言われたそうです。客室の通路は、座席の乗客が移動する場所なので、そこに立ち続けることは認められていないんです。
デッキに立つ場合は、他の人の邪魔にならないように配慮する。これが最低限のマナーです。

新幹線で立ち乗りになるパターン5つ
①指定席を予約せずに乗車した場合
最も基本的なパターンが、「指定席を予約せずに乗車する」ケースです。
急な出張や予定変更で、今すぐ新幹線に乗らなければならない。でも指定席を予約する時間がない、またはすでに満席。そんな時、乗車券と特急券だけを買って、立ち乗り覚悟で新幹線に乗ることができます。
みどりの窓口や券売機で「乗車券+特急券(指定席なし)」を購入すれば、全席指定の新幹線でも乗車できます。ただし、座席はないので、デッキに立つことになります。
このパターンは、短距離移動(東京〜品川、新横浜〜名古屋など)で利用されることが多いです。「10〜30分くらいなら立っていてもいいか」という判断ですね。
券売機での購入方法を知らない人も多いので、ここで簡単に説明しておきます。券売機で「新幹線特急券」を選択し、乗車区間を入力すると、「指定席」「自由席」などの選択肢が表示されます。全席指定の列車(のぞみ、はやぶさなど)の場合、「指定席」しか選べないことが多いですが、「座席を指定しない」という選択もできます。これを選ぶと、指定席料金なしの特急券が購入できます。ただし、座席はないので、デッキに立つことになります。わからない場合は、みどりの窓口で「指定席なしの特急券をください」と言えば、窓口の方が対応してくれます。
②乗り遅れて後続列車に乗った場合
予約していた指定席の列車に乗り遅れた。このパターンも非常に多いです。
新幹線の指定席は、予約した列車にしか乗れません。でも、乗り遅れた場合は救済措置があります。当日中の後続列車に、立ち乗りで乗車することができるんです。
例えば、10時発の「のぞみ」の指定席を予約していたのに、遅刻して乗り遅れた。次の10時30分発の「のぞみ」に飛び乗ることができます。ただし、指定席は無効になるので、座席はありません。デッキに立つことになります。
このルールは、乗り遅れた乗客への救済措置。指定席料金は無駄になりますが、少なくとも目的地には到着できます。
【乗り遅れた時のポイント】
・当日中の後続列車に立ち乗りで乗れる
・指定席料金は戻らない
・乗車券と特急券は有効
・みどりの窓口で次の列車の指定席に変更も可能(空席があれば)
③満席で指定席が取れなかった場合
繁忙期や週末、人気の時間帯は、指定席が満席で取れないことがあります。
「どうしてもこの時間に移動したい」という場合、立ち乗りを覚悟で新幹線に乗る人がいます。特に帰省や旅行の予定を変更できない場合、満席でも乗るしかないんです。
私も一度、お盆の時期に東京から大阪へ移動する際、のぞみの指定席が全て満席でした。でも仕事の都合でどうしてもその日に移動しなければならず、立ち乗り覚悟で特急券だけを買って乗車しました。新大阪までの2時間半、ずっと立ちっぱなし。正直、かなりキツかったです。
満席の場合、自由席がある「ひかり」や「こだま」に変更するのも一つの手。全席指定の「のぞみ」で立つよりは、自由席がある列車で座れる可能性を探る方が賢明かもしれません。
実は、繁忙期に賢く新幹線を利用するコツがあります。それは、「のぞみ」ではなく「ひかり」や「こだま」を選ぶこと。のぞみは速くて人気ですが、その分満席になりやすい。一方、ひかりやこだまは少し時間はかかりますが、比較的空いていることが多いです。特に「こだま」は、各駅停車なので敬遠されがちですが、その分自由席に座れる可能性が高いんです。
私の経験では、お盆の時期に東京から名古屋に移動する際、のぞみの指定席が全て満席だったことがあります。みどりの窓口で相談したところ、「こだまなら自由席に座れる可能性がありますよ」と提案されました。実際に「こだま」に乗ってみると、自由席は7割程度の乗車率で、無事に座ることができました。のぞみなら2時間のところ、こだまは3時間かかりましたが、座って移動できたので快適でした。時間に余裕があるなら、こだまを選ぶのも賢い選択です。
④途中駅から乗って席が空いていない場合
新幹線の指定席は、始発駅から終着駅までの長距離利用が多いです。途中駅で降りる人は少なく、途中駅から乗ろうとすると、すでに座席が埋まっていることがあります。
例えば、東京発の「のぞみ」は東京〜新大阪、東京〜博多の利用が多い。品川や新横浜から乗ろうとすると、すでに指定席が満席、ということがよくあります。
途中駅から乗る場合で、指定席が取れなかった時。立ち乗りになる可能性が高いです。特に週末や繁忙期は、途中駅での座席確保は難しいと考えておきましょう。
私も一度、品川から新幹線に乗ろうとして、このパターンにはまったことがあります。東京始発の「のぞみ」は、東京〜新大阪、東京〜広島といった長距離利用が多く、品川時点ですでに満席。指定席を取ろうとしたら、その日の列車は全て満席でした。急いでいたので、立ち乗り覚悟で特急券だけを買って乗車。品川から新横浜までわずか18分でしたが、デッキに立っているのは思った以上に窮屈で、「次からは早めに予約しよう」と決めました。
途中駅からの乗車が多い人(品川、新横浜、名古屋、京都など)は、特に注意が必要です。始発駅からの長距離利用者が多いため、途中駅での空席は少なくなります。途中駅から乗る場合は、できるだけ早めに指定席を予約するか、自由席がある「ひかり」や「こだま」を選ぶのが賢明です。
⑤短距離移動でわざと立ち乗りを選ぶ場合
これは意外かもしれませんが、わざと指定席を取らずに立ち乗りを選ぶ人もいます。
理由は、「短距離だから立っていても平気」「指定席料金を節約したい」というもの。例えば、東京〜品川(6分)、新横浜〜名古屋(約50分)など、比較的短い区間なら、立っていても我慢できる範囲です。
特にビジネス客の中には、「名古屋まで50分くらいなら立っていてもいいや」と考えて、指定席料金を浮かせる人もいます。指定席料金は往復で2,000円以上かかることもあるので、節約志向の人には魅力的に見えるんですね。
私の知人にも、こうしたタイプの人がいます。彼は月に数回、東京〜名古屋間を出張で往復しているのですが、いつも立ち乗りだそうです。「50分くらいなら立っていても平気。その分、浮いた指定席料金でランチを豪華にできる」と笑っていました。若くて体力があるからこそできる選択ですね。
ただし、立ち乗りは体力的にキツイです。荷物を持っていたり、疲れていたりする場合は、素直に指定席を取った方が快適です。節約も大事ですが、健康と快適さも大事。バランスを考えて選択しましょう。
また、短距離移動でも繁忙期は要注意です。デッキが混雑していると、短時間でもかなりのストレスになります。年末年始やゴールデンウィークなどは、短距離でも指定席を取った方が無難です。
立ち乗りの料金はどうなる?指定席料金は払う必要ある?
立ち乗りでも乗車券と特急券は必要
立ち乗りの場合、料金はどうなるのか。これ、気になりますよね。
結論から言うと、立ち乗りでも「乗車券」と「特急券」は必要です。座席がないからといって、タダで乗れるわけではありません。
新幹線に乗るために必要な切符は、次の2つです。
- 乗車券:JRの路線に乗るための基本料金(区間に応じて変動)
- 特急券:新幹線という特急列車に乗るための追加料金
立ち乗りの場合、この2つは必ず必要です。改札を通る時にチェックされますし、車内で車掌さんが検札に来た時にも提示を求められます。
「立っているんだから安くしてよ」と思うかもしれませんが、JRの規則では、乗車する以上は乗車券と特急券が必要、とされています。
指定席料金は不要だが特急料金は必要
では、「指定席料金」はどうなるのか。
立ち乗りの場合、指定席料金は不要です。座席を使わないのだから、指定席料金を払う必要はありません。
でも、「特急料金」は必要です。新幹線という特急列車に乗っている以上、特急料金は払わなければなりません。
この違い、わかりますか?
| 料金の種類 | 立ち乗りの場合 | 指定席の場合 |
|---|---|---|
| 乗車券 | 必要 | 必要 |
| 特急券 | 必要 | 必要 |
| 指定席料金 | 不要 | 必要 |
つまり、立ち乗りの場合は「乗車券+特急券」だけでOK。指定席の場合は「乗車券+特急券+指定席料金」が必要、ということです。
のぞみ・はやぶさでも立ち乗り可能だが料金は同じ
「のぞみ」や「はやぶさ」のような全席指定の列車でも、立ち乗りは可能です。
ただし、料金は「ひかり」や「こだま」と同じというわけではありません。のぞみの特急料金は、ひかりやこだまよりも高く設定されています。
例えば、東京〜新大阪の特急料金(通常期)は次の通りです。
- のぞみ(指定席):5,810円
- ひかり(指定席):5,810円
- ひかり・こだま(自由席):4,960円
立ち乗りの場合、のぞみでもひかりでも、特急料金は指定席と同じ金額を払います。座席がないのに、指定席と同じ料金を払うのは少し損した気分になりますが、これがルールです。
「え、立っているのに指定席と同じ料金?おかしくない?」と思う気持ち、よくわかります。私も最初はそう思いました。でも、JRの考え方は「特急列車に乗る以上、特急料金は必要」というもの。座席の有無は関係なく、新幹線という特急列車を利用しているのだから、特急料金を払ってください、というスタンスなんです。
もし料金を節約したいなら、自由席がある「ひかり」や「こだま」を選んで、自由席特急券を買う方がお得です。自由席特急券なら、指定席より850円安くなります。東京〜新大阪なら、往復で1,700円の節約。これは大きいですよね。
ただし、ひかりやこだまは、のぞみより時間がかかります。東京〜新大阪の場合、のぞみなら約2時間30分ですが、ひかりなら約3時間、こだまなら約4時間かかります。時間を取るか、料金を取るか。この選択は、あなたの状況次第です。
急いでいるなら、のぞみで立ち乗りもやむを得ません。でも、時間に余裕があるなら、ひかりやこだまの自由席を狙った方が、座れる可能性も高く、料金も安くなります。賢い選択をしましょう。
実際の料金例(東京→新大阪、東京→仙台など)
実際に、立ち乗りの料金がいくらになるのか、具体例を見てみましょう。
東京→新大阪(のぞみ・立ち乗り)
- 乗車券:8,910円
- 特急券:5,810円
- 合計:14,720円
東京→新大阪(のぞみ・指定席)
- 乗車券:8,910円
- 特急券(指定席込み):5,810円
- 合計:14,720円
あれ、同じ料金?そうなんです。立ち乗りでも、指定席でも、料金は同じ。座席がないのに同じ料金を払うのは、正直納得いきませんが、これが現実です。
東京→仙台(はやぶさ・立ち乗り)
- 乗車券:6,050円
- 特急券:6,010円
- 合計:12,060円
- 広さは3〜4平方メートル程度
- トイレ、洗面台、荷物置き場がある
- 窓がある車両もある(景色が見える)
- 床に滑り止めのマットが敷かれている
- トイレのドアの前:トイレを使う人の邪魔になる
- 荷物置き場の前:荷物を取りに来る人の邪魔になる
- 洗面台の前:手を洗いたい人の邪魔になる
- 車両の扉の前:駅で乗降する人の邪魔になる
- 当日中の列車に限る(翌日以降は無効)
- 同じ区間の列車に限る(東京〜新大阪など)
- 指定席は無効になる(座席には座れない)
- 指定席料金は戻らない
- 後続列車に空席があること
- 当日中の列車であること
- 乗車前にみどりの窓口で手続きすること
- 乗り遅れた場合:指定席料金は返金されない
- 自分の判断で指定席を取らなかった場合:返金の対象外
- 満席で指定席が取れなかった場合:最初から指定席を買っていないので返金の対象外
- 指定席に他の乗客が座っている
- 空席があるかどうか知りたい
- 長時間の立ち乗りで体調が悪くなった
- 次の列車の指定席を変更したい
- デッキの荷物置き場(専用スペースがある車両もある)
- 自分の足元(自分で管理できる範囲)
- 壁際(通行の邪魔にならない場所)
- トイレのドアの前
- 通路の真ん中
- 車両の扉の前(駅で乗降する人の邪魔になる)
- 1時間以上の長距離移動
- 大きな荷物を持っている
- 混雑していて身動きが取れない
- 疲れている、体調が悪い
- できるだけ早めに指定席を予約する(乗車日の1ヶ月前から予約可能)
- 自由席がある列車(ひかり、こだま)を選ぶ
- 空いている時間帯を選ぶ(平日の昼間、深夜など)
- どうしても立ち乗りになる場合は、途中駅で座れる可能性を探る
- こまめに足を動かして血行を良くする
- 水分補給を忘れずに(脱水症状に注意)
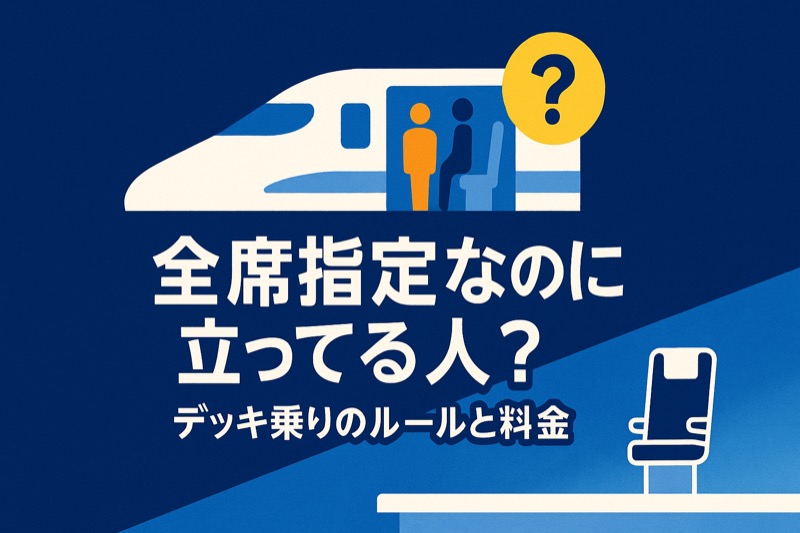









コメント